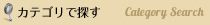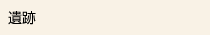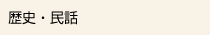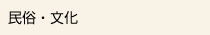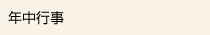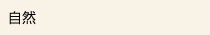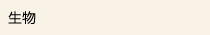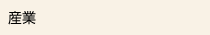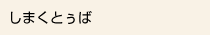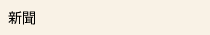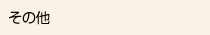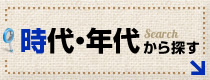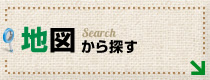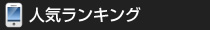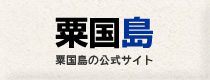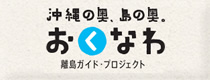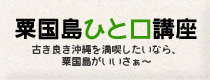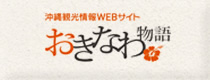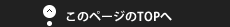ホーム > 検索条件:「」
検索条件:「」9058件を表示
-
-
ツマグロキチョウ
秋に迷蝶として採集されることがある。沖縄で採集されるものは、本土に比べて翅の表面が赤い。9月ごろに北風が吹くころから北の朝鮮半島や大陸から飛んで来るものと考えられている。前翅の前緑部が角ばるので、近似種のキチョウと見分けることができる。
...カテゴリ:生物 ・ 昆虫・動物
-
-
-
ツマグロヒョウモン
荒地や海岸線でよく観察できる。1属1種の蝶で、その分布地が温帯から熱帯にあることなど、特に大型のヒョウモン類の中では異色な存在。ヒョウモンという名は、翅の斑紋がヒョウのようである為付けられたとされている。雄雌の斑紋に違いがあり、雌は前翅頂に...
カテゴリ:生物 ・ 昆虫・動物
-
-
-
ツマベニチョウ
成虫は、前翅長40~55mmと中型種では大きい方で、シロチョウの仲間では世界的に見ても最大級である。翅のオスは地色は白色であるが、メスは黄白色から灰白色まで幅がある。前翅端には鮮やかな赤色(端紅マツベニ)で、その赤色の周りは、黒色で縁取られ...
カテゴリ:生物 ・ 昆虫・動物
-
-
-
ツミ
雄の上面は暗青灰色、下面は白くて胸側から脇は黄赤褐色で、目は暗紅色。雌の上面は暗石板色で下面の横斑は太くて粗い。雌雄・幼鳥とも目の外縁が黄色。八重山諸島には亜種リュウキュウツミ(A. g. iwasakii)が生息する。ツミとリュウキュウツ...
カテゴリ:生物 ・ 野鳥
-
-
-
ツメクサ
庭や道ばた、砂まじりの畑地などで良く見られる1~2年生草本です。茎は根もとから叢生し、高さ5~15㎝くらい。葉は線形で先はとがり、対生します。花は小型で白色。和名は、葉の形が鳥のツメに似ているので名づけられました。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツヤの祠(共通語)
上原英昌
性別:男
記録日:1982年9月20日
記録場所:沖縄県粟国村中央公民館カテゴリ:歴史・民話 ・ 民話
-
-
-
ツヤの祠
字浜の港近くにある祠。番所(ばんじゅ)がある頃の話。番所とは、近世に置かれた島の役所。字西にあり、後に浜に移された。首里から派遣された役人と島出身の役人が島を治めていた。『琉球国由来記』によれば、粟国島の番所役人は地頭代の新里大屋子、首里大...
カテゴリ:歴史・民話 ・ 民話
-
-
-
ツヤハナグムリ
ドウガネ類と似ているが、ハナムグリ類は角ばった体型をし、上翅を閉じたまま上翅と腹部の隙間から後翅を出して飛ぶ。ハナムグリという名前から花に潜るような印象を与えるが、ミカンの樹液や熟した果実の方を好む。近似種にリュウキュウハナオオハナムグリが...
カテゴリ:生物 ・ 昆虫・動物
-
-
-
ツユベラ
幼魚と成魚で色彩が大きく異なる。幼魚は赤みを帯びた体で、体側に白色斑がある。成長すると体に青い斑点が現れ、成魚では背鰭の第1棘がやや伸びる。尾鰭は丸みを帯び、後半部は黄色になる。
サンゴ礁やその周辺の砂底に生息する普通種。期間が迫ったとき...カテゴリ:生物 ・ 海洋生物
-
-
-
釣り場(ダイビングポイント)
粟国島周辺海域のダイビングポイントの1つ。粟国島のダイビングポイント名は、島の屋号と美南海の開拓時のスタッフの名前を命名している。
カテゴリ:産業 ・ 漁業
-
-
-
ツルグミ
陽あたりのよい山裾や林縁などに普通に見られる常緑の藤本です。茎は半つる性で、長くのび、長さ3~5mくらいになります。葉は長楕円形で先はとがり、裏面には赤褐色の鱗片を密布し、互生します。核果は長楕円形で赤紅色に熟します。蔓グミの名は、枝がつる...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルナ
海岸の砂地などに多く見られる多肉質の1年生草本です。茎は稜があり、ほふくして長さ20~50㎝くらいになり、若枝には腋点が沢山あります。葉は多肉質で菱形状卵形、先は鈍くとがり互生します。花は1~2個葉腋につき花弁はなく、内面が黄色をした筒状の...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルナシインゲン
葉は長さ10cmほどのひし形の小葉3枚からなる複葉で,長い柄をもつ。つる性のものは支柱に巻きついて1.5~3mに伸びるが,ツルナシインゲンは高さ30cm内外の矮性(わいせい)である。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルノゲイトウ
海岸近くの湿地から山手にかけ、普通に見られる半つる性の草本です。茎は円柱形で地上をはい、長さ50㎝くらいになります。葉は倒披針形で対生します。和名は蔓野鶏頭の意で、ノゲイトウに似ていて、茎がつる状になるので名づけられました。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルボ
陽あたりのよい草地に生える多年生草本。鱗茎は卵球状、外皮は黒褐色、長さ約2~3㎝、葉は線状倒披針形で暗緑色をし、先はとがります。秋になると相対した葉の間から花茎を出し、先端に長さ約3~10㎝の穂状花序をつけ、淡紫色の小さな花を密に咲かせます...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルマオ
多年生草本で茎は細く、つる状に1mくらいまでのびます。葉は長楕円状状披針形で先はとがります。花は黄緑色で小さく、雌株と雄株の区別があります。和名は蔓苧麻の意で、茎がつるになるところから名づけられました。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルムラサキ
熱帯アフリカ原産のつる性草本です。茎や葉は多肉質で毛はありません。初夏から秋にかけて、葉腋から長い花軸を出し、多くの花をつけます。挿木で簡単にふやせます。和名のツルムラサキは、茎がつるになり果汁から紫色の染料がとれるところから名づけられたと...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツルモウリンカ
海岸の岩場または砂地に多く見られる多年生のつる性草本で、茎は30~100㎝くらいになり、若枝には淡褐色の軟毛があります。葉は卵状楕円形、全縁で先はにぶくとがり、表面や裏面には縮毛を散生します。花は淡黄色の小さな花で中心部はいくぶん紫色を帯び...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ツンベルギア
キツネノマゴ科ツンベルギア属の総称。多年草または低木でつる性の種類もあり、熱帯アフリカ、マダガスカル島、熱帯アジアに約100種分布する。以下の各種がよく知られる。アラータT. alata Bojerは熱帯アフリカ原産のつる性多年草であるが、...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ティサノゾーン・ニグロパピッロスム
体は扁平で柔らかく頭部の縁は触角状に捲れる。体地色は黒色で白縁。背面に黄色く細かい疣状の突起が散在。
カテゴリ:生物 ・ 海洋生物
-