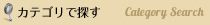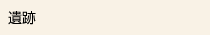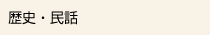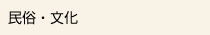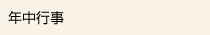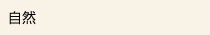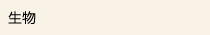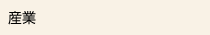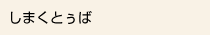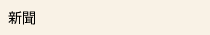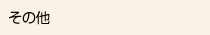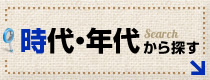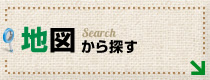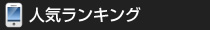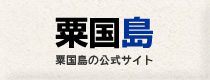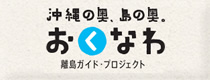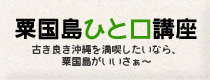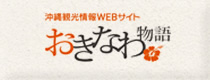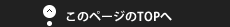ホーム > 検索条件:「」
検索条件:「」9058件を表示
-
-
ギョボク
石灰岩地帯に多く見られる落葉性の小高木。幹は直立して高さ4~8mくらいになり、小枝には赤褐色で多数の皮目があります。葉は長柄のある3出複葉、小葉は披針形で長さ10㎝内外、表面は緑色、裏面は灰白色をし、先はとがります。魚木の名は、材質がやわら...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ギンチョウ
マダガスカル原産。海岸や人家の石垣で見られる。潮風などに邪魔されなければ背が高くのびる。繁殖力が強く、手を焼く雑草でもある。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
ギンムクドリ
雄では頭部が橙黄色、喉と上胸は白い。体は紫灰黒色で後頭から上胸にかけてが濃い。翼と尾は黒くて一部に白色がある。腰は淡色で、下腹と下尾筒は白く、くちばしと足は橙色。雌は頭部が黄褐色で、体は灰褐色、足は橙赤色。
カテゴリ:生物 ・ 野鳥
-
-
-
ギンユゴイ
本科魚類としてはめずらしく、一生を海で過ごす。幼魚はタイドプールにいる普通種。尾鰭に5本の黒色帯があり、他種との区別は容易。
体は強く側扁していて細長く、尾柄は長い。体色は銀白色で、背部は少し青味を帯びている。鱗は櫛鱗で、眼は大きく、口は...カテゴリ:生物 ・ 海洋生物
-
-
-
ギーチャーオーエー(片足戦争)
片足をあげ、片手で足をにぎり(右手で左手をつかまえる)、片足を手放した方が負けとなる。
カテゴリ:民俗・文化 ・ 風俗
-
-
-
ギーマ
林縁に生える。高さ1~3mの常緑低木。若枝には短軟毛が密生するが、まもなく無毛となる。葉は革質で互生し、葉柄は長さ2-3mm、ほとんど無毛。葉身は楕円形で先はとがり、長さ2-5㎝、幅1-2.5㎝、両面とも無毛、縁には先のやや鈍い鋸歯がある。...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クガニダマユーエー
白紙に包んだ二合飯を大工の頭領が東側の屋根の上にあがり、そこから、「クガニダマウトスンドゥー、ナンザダマウトスンドゥー、ウマヌウミングワスタマウトスンドゥー」と言った文句を唱えて落とす。それを軒下で晴着の戸主が、着物を広げて受け取る。二合飯...
カテゴリ:民俗・文化 ・ 風俗
-
-
-
ククヤムイ
学校、役場、診療所など村の行政機関等が集中する東地区の中央公民館やや西側に位置する。東地区は、明治12年4月に廃藩置県で琉球藩が廃止時に八重村が廃止され更に明治36年に西村、東村を廃止し、区制施工され現在の字西、字東、字浜と改称された。牛馬...
カテゴリ:民俗・文化 ・ 文化財
-
-
-
クグ
日あたりのよい草地に生える多年草。稈の基部に卵状の塊茎があり暗赤紫褐色の旧鞘に包まれる。稈は直立しやや太く、高さ30-80㎝、基部に数個の葉がある。葉は短く、多少外反し、幅は3-6mm、鞘は暗赤褐色を帯びる。花は8-10月。花序は単純、枝は...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クグガヤツリ
日あたりのよい田畑や道ばたに生える1年草。稈は数個そう生し、高さ10-30㎝、葉は少数で稈より低く、幅は1-3㎜、鞘は紅褐色を帯びる。花は8-10月。花序は単純、長さ幅共5-10㎝。総苞片は2-3個、花序より長い。枝は1-4本、時に全く発達...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クグテンツキ
日本南部に生え2年生。2年目の植物では葉はやや無毛、花序は複製生、小穂は数個集まった型となる。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クコ
中国、日本原産の小低木で高さは1.5mぐらいになります。夏から秋にかけて淡紫色の小さい花が咲きます。和名のクコは枸杞の音読みです。薬用。
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クササンダンカ
熱帯アフリカの高地の林やサバナ、草地によく見られる低木だが、大きいものは高さ1.3mにもなる。全体に軟毛が多く、葉は披針形で、日陰の葉はよく生育し、長さが10㎝を越える。たくさんの花が頭状に集まって咲く。花冠は細長い筒の長さが約2㎝、裂片は...
カテゴリ:自然 ・ 植物
-
-
-
クサシギ
夏羽は頭と体の上面が灰黒褐色で小さな白斑があり、上尾筒は白く、尾も白くて先に黒斑がある。顔から胸は白地に黒褐色の縦斑が密にあり、眉斑は短くて、目の外縁の白色部とつながっている。足は灰緑色。冬羽では体の上面の斑点が少し褐色をおび、密になってい...
カテゴリ:生物 ・ 野鳥
-
-
-
草戸原と島建て
草戸原は粟国島の西北端近くで、粟国島では最も高い丘陵にある。粟国島に限らず、昔の村が意外に高い丘の上や山の中腹で始められたという伝承が多い。
島建てとは村を始めることを言う。
●この島の始まりは草戸原からだと言う。一帯にはたくさんの洞窟...カテゴリ:歴史・民話 ・ 民話
-
-
-
草戸御嶽
粟国島の最北端近くで島では最も高い丘陵にある草戸原において、粟国島の島建て(村を始めること)がなされたという話が粟国島の民話「草戸原と島建て」で紹介されている。近くにはハバーサクの洞窟やアサギンエイがある。
カテゴリ:民俗・文化 ・ 文化財
-
-
-
草戸折目
草戸折目。四月二十日前後に行う。これは農作物の祈願日で、昔は神酒を供え、ショウバを各家庭より30匁(もんめ)出し、それをそなえた。現在は村予算で実施している。
カテゴリ:年中行事 ・ 伝統行事
-
-
-
草戸原と島建て(方言)
上原英昌
性別:男
記録日:1982年9月21日
記録場所:沖縄県粟国村 上原氏宅カテゴリ:歴史・民話 ・ 民話
-
-
-
草戸節
一、草戸から下りて 夜ふけてぃくりば 夜から押す風や な冷るさぬ 二、夜原押す風や 足からが入ゆら 裾からど入ゆら な冷るさぬ 三、わが草戸島や 瓢箪ない所 赤皿の飯(ンバイ) ひなかおしる 四、わが草戸島や水欲さんねらん 池小堀掘て ふか...
カテゴリ:民俗・文化 ・ 風俗
-
-
-
クシレージ(ダイビングポイント)
粟国島周辺海域のダイビングポイントの1つ。粟国島のダイビングポイント名は、島の屋号と美南海の開拓時のスタッフの名前を命名している。ダイビングスポット「屋岸」より下(南に下った)にあるスポット。
カテゴリ:産業 ・ 漁業
-